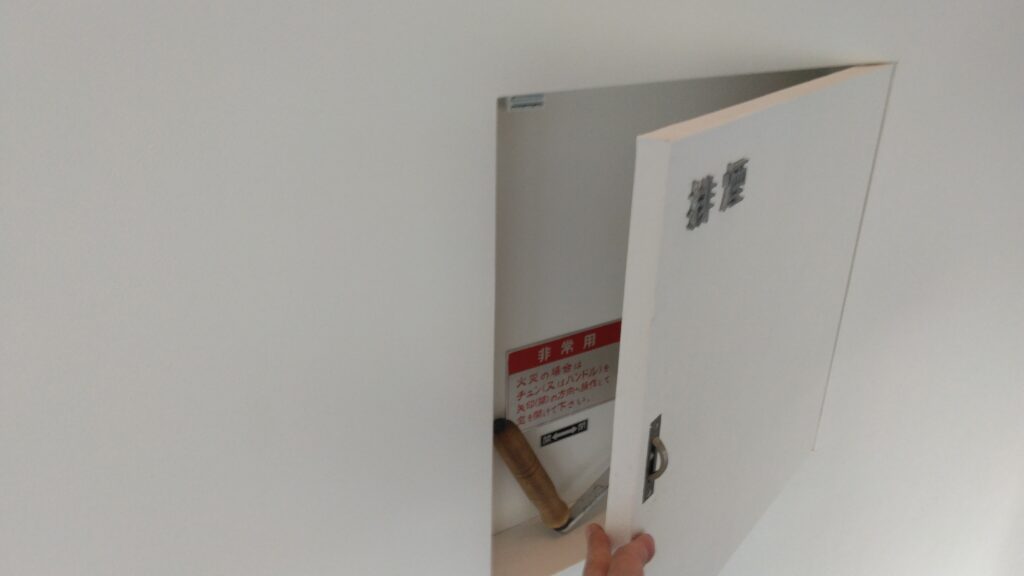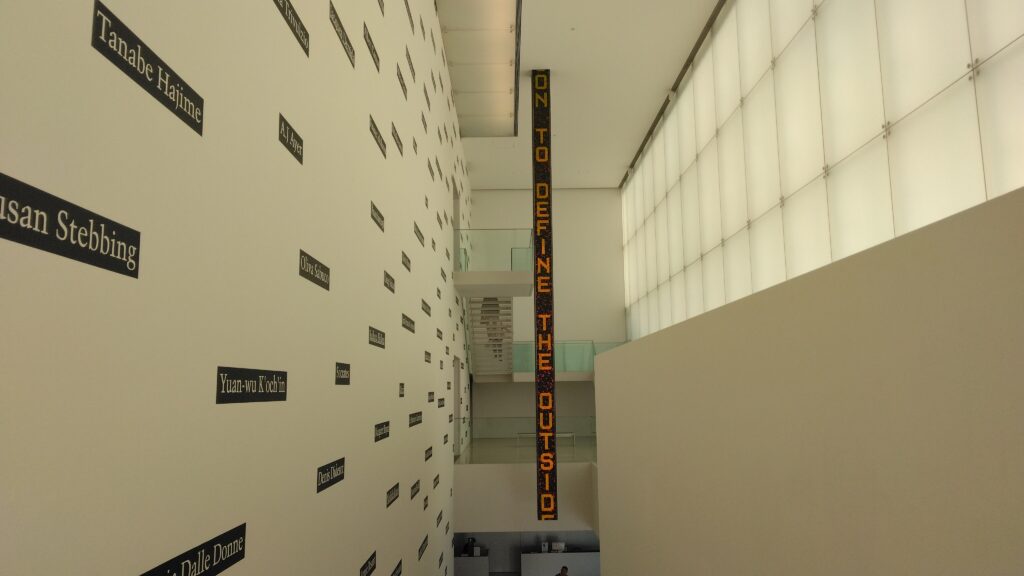〔設問1〕課題1.本件訴訟の被告が甲となるような見解、乙となるような見解について
・当事者(意義)
:自己の名において訴え、または訴えられることによって判決の名宛人となる者
・当事者の特定(意義)
:誰が誰に対して当該訴えを提起するのかを明らかにする原告の行為
・当事者の確定(意義)
:裁判所が特定の事件の当事者が誰であるかを判断する作業
・形式的表示説
:当事者の確定に当たって、訴状の当事者欄の記載のみを基準
↓
本件訴状の当事者欄には「被告Mテック、代表者A」と記載されており、乙のことを指している
↓したがって、
この見解によれば乙が被告となる
・実質的表示説(通説)
:当事者欄の記載に限らず、請求の趣旨・原因その他記載事項を含めて、訴状の全体から総合的に当事者を確定
↓
本件訴状の当事者欄に記載されている「被告Mテック、代表者A」とは訴状の請求の趣旨・原因を見る限り、Xが本件賃貸借契約を締結した会社である。その時点では乙は存在していなかったのだから、訴状において表示されている被告は乙と商号・代表者が元々同一であった甲を意味している
↓したがって、
この見解によれば甲が被告となる
・参考判例 法人格の実質的同一性(最判S48.10.26 6)
〔設問1〕課題2.仮に被告を乙と確定した場合、裁判所は第2回口頭弁論期日における乙の代表者としてのAの陳述につき、自白が成立していると取り扱うべきか。仮に自白が成立しているとすると、再開後の第3回口頭弁論期日における自白の撤回をどのように取り扱うべきか。
・自白(意義)
:相手方の主張を争わない旨の当事者の陳述、または、その結果として生じた当事者間に争いのない状態
・裁判上の自白(意義)
:訴訟の口頭弁論または弁論準備手続において、当事者の一方が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のこと
↓(要件)
1)口頭弁論または弁論準備手続における弁論としての陳述であること(弁論としての陳述)
2)事実についての陳述であること(事実の陳述)(判例は主要事実のみ)
3)相手方の主張との一致があること(主張の一致)
4)自己に不利益な陳述であること(不利益性)(判例:証明責任説(相手方の証明責任からの解放))
・自白の効果
1)証明不要効(179)
:自白された事実は証拠による証明を要しないものとする効果
2)判断拘束効
:裁判所は自白された事実を必ず判断の基礎にしなければならないとする効果
3)審理排除効
:裁判所は自白された事実に関して審理を行ってはならないものとする効果
4)撤回制限効
:当事者は自白の撤回ができなくなるものとする効果
↓(例外)
・自白撤回の要件
1)相手方が自白の撤回に同意した場合
2)相手方または第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をするに至った場合(338Ⅰ⑤)
3)自白された事実が真実であるという誤信に基づいて自白がなされた場合(参考判例 自白の撤回の要件(大判T4.9.29 53))
・本件では、Aは、第2回口頭弁論期日において、相手方Xが証明責任を負う、請求原因事実について、これを認めている
↓したがって、
自白の要件に照らして、自白が成立していると評価できる
・Xが問題文中で主張する事実は、実際にはXと甲との間で起こった事実であって、Xと乙との間で起こった事実ではない。したがって、甲と乙が別人格であることを前提とする限り、Aの陳述は真実に反すると評価できる。しかし、Aの当該自白は訴訟を遅延させることを目的としたものであって、自白事実が真実であると誤信したことに基づくものではない
↓したがって、
Aの自白は錯誤に基づくものではないことを理由に撤回できない
〔設問2〕甲を被告に追加するXの申立ては認められるか
・主観的追加的併合(意義)
:係属中の訴訟において、当事者を追加すること
・参考判例 主観的追加的併合(最判S62.7.17 91)
:主観的追加的併合を否定する理由
1)併合前の訴訟状態を新たに追加された当事者との関係で当然に利用できる保障がなく、かえって訴訟を複雑化させるおそれがある
2)軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれがある
3)事後的に共同訴訟を作り出したければ新たに被告として追加したい者を相手取って別訴を提起した上で裁判所による弁論の併合を待てば足りる
・従前のX乙間の訴訟状態をX甲間の訴訟において利用し、審理の重複を省略することで訴訟経済に資すると言える。また、両訴訟を併合して審理を行うことはその審理の中でAが乙を設立した経緯等が明らかにされることで、本件の紛争実態に即した矛盾のない判断が可能になるため、訴訟を簡明にすると言える。さらに、上記理由により訴訟の遅延も防止することが期待される。また、Aの不誠実な行為がある本件に限ってXに主観的追加的併合を認めても軽率な提訴が誘発されることはないと考えられる
↓したがって、
Xの主観的追加的併合の申立ては認められる
〔設問3〕「文書」の定義。また、USBメモリが「文書でないもの」に当たることを論証すること。その上で、USBメモリを取り調べることが許容される理由を明らかにすること
・文書(意義)
:文字やその他記号によって、作成者の思想を表現した有形物
・書証(意義)
:文書に記載されている作成者の意思や認識を閲読して読み取った内容を事実認定のための資料とする証拠調べ
・文書に準ずる物件への準用(231)
:この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する
・USBメモリは文書に当たらないが、一定の情報を表現できるという点で文書ないしテープ類に類似する。
↓したがって、
USBは「その他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの」(231)に該当する
・「文書でないもの」(231)は書証の方法による証拠調べに馴染む
↓したがって、
USBを書証によって取り調べることは許容される
:LEGAL QUEST 民事訴訟法〔第4版〕・三木浩一、笠井正俊、垣内秀介、菱田雄郷(有斐閣)
民事訴訟法判例百選〔第6版〕(有斐閣)
司法試験の問題と解説2022・法学セミナー編集部(日本評論社)