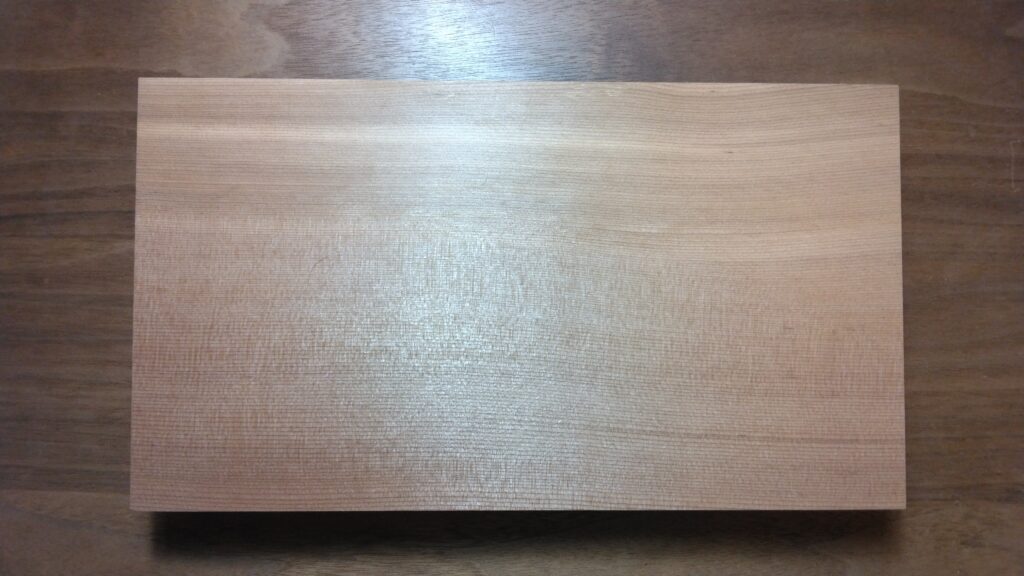〔設問1(1)〕AB間の通謀虚偽表示における第三者CがAに対して甲土地の引渡しを請求したことに対し、Aはこれを拒むことができるか。
・通謀虚偽表示
:真意でない意思表示であって、意思表示の相手方との間に通謀があった場合
↓(原則)
通謀虚偽表示は無効(94Ⅰ)
↓(例外)
当事者は善意の第三者に対しては、通謀虚偽表示であることを理由とする無効を主張することができない(94Ⅱ)(無過失は要しない)
↓
・第三者
:新たにその当事者から独立した利益を有する法律関係に入り、法律上の利害関係を有するに至った者
・不動産物権変動と第三者
↓
公信の原則
:ある権利がある権利主体に帰属していないにもかかわらず、その者にその権利が帰属しているかのような公示がされている場合には、この外形を信頼して取引に入った者は外形に対応する権利を取得すること
↓
動産については認められるが(192)、不動産については認められない
↓ただし、94条2項類推適用し、
虚偽の外形(不実の登記)の作出(AB間)につき帰責性(非難可能性)のある真の権利者(A)は保護に値せず、外形(登記)を信頼して取引に入った第三者(C)の保護の必要性、を理由に第三者の保護を図る
↓
①意思外形対応型(外形自己作出型(積極的意思)、外形他人作出型(黙認))
(Aに通謀虚偽表示の認識有り、帰責性大)
→94条2項類推適用により第三者を保護
↓(要件)
(ⅰ)Cが取引行為により甲土地所有権を取得したこと
(ⅱ)取引行為時に甲土地の登記名義がBであったこと
(ⅲ)取引行為時に、Bが所有者であるとCが信じたこと
(ⅳ)甲土地所有権の登記名義人がBであったことについてのAの意思的関与
②意思外形非対応型
(Aに通謀虚偽表示の認識はあるが善意、帰責性中)
→94条2項類推適用+110条の法意により第三者を保護
↓(要件)
(ⅰ)~(ⅳ)は上記と同じ
(ⅴ)Bを所有名義人とする登記を真実と信頼したことにつき、Cに正当な理由があったこと
③本人の意思によらない外形作出型
(Aに通謀虚偽表示の認識がない、帰責性小)
→94条2項+110条類推適用により第三者を保護
↓
「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いものというべき」場合に、「民法94条2項、110条の類推適用により」虚偽の外観を信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がなかった第三者の保護を認めている(民法94条2項・110条の類推適用 最判H18.2.23 Ⅰ-22)
・BC間で甲土地に関して売買契約(555)を締結しているが、所有権は依然としてAに在り、Cは甲土地の所有権を取得できない
↓しかし、
Cは甲土地についてBの所有権移転登記という虚偽の外観を信頼した結果、契約を締結している。登記に公信力はないが、94条2項の第三者として保護されないかが問題となる(本人の意思によらない外形作出型)
↓
AB間の契約は通謀虚偽表示ではないため、94条2項を直接適用できない。だが、同条同項の基礎にある権利外観法理に鑑みれば、虚偽の外観、真正権利者の帰責性、外観に対する正当な信頼があり、本人の意思によらない外形を作出したのであれば、94条2項と110条を類推適用してCを保護しうる
↓本問においては、
Aは抵当権の抹消登記手続を委託したBの言葉を信じ、所有権移転登記手続に必要な書類一式を交付したことは帰責性を基礎づける。しかし、その行為は不動産取引の経験のないAがBの巧みな虚言に騙されたためである。Aが知るすべなくBは契約書の偽造を行い、短期間でCとの間で契約を締結している。これら事実に照らすと、Aに外観作出に積極的関与やあえて放置した事情は見られず帰責性を認めることはできないため、94条2項、110条の類推適用はできない
↓よって、
CはBの登記の外観が虚偽であることをAに対抗することができず、所有権を取得することはできないため、CがAに対して甲土地の引渡しを請求したことに対し、Aはこれを拒むことができる
〔設問1(2)〕AD間で甲土地の売買契約が締結されたが代金支払いは終えたが移転登記は未了。その間にAB間で売買契約し代金支払いと移転登記が完了。さらにBC間で売買契約し代金支払いと移転登記が完了。D(相手方)はC(転得者)に対し、甲土地につき、Dへの所有権移転登記手続をするように請求し(請求1)、それができないとしても、A(当事者)への所有権移転登記手続するように請求(請求2)した。それぞれの可否について。
・「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記
:所有権を有していない登記名義人のもとから所有権を有している者への登記名義を回復するための「真正な登記名義の回復」を登記原因とする所有権移転登記
・所有権の移転
:「当事者の意思表示のみによって」その効力を生じる(176)
・公示の原則
:買主が物権変動の事実を第三者に主張するためには当該物権変動が公示されていなければならない
・不動産物権変動の公示は登記(177)
・第三者
:物権取得等につき、登記の欠缺を主張するのに正当な利益を有する者(悪意者を含む)
・背信的悪意者
:登記の欠缺を主張することが信義に反する者
↓(要件)
1)物権変動があった事実についての悪意
2)信義に反するものと認められる事情
・参考判例 民法177条の第三者の範囲(2)-背信的悪意者からの転得者 最判H8.10.29 Ⅰ-61
:背信的悪意者からの転得者は転得者自身が背信的悪意者でない限り、第三者として保護される(相対的構成)
・請求1について
DはCに対し、請求1をもって真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求を行使している。これに対し、Cは177条にいう第三者であり、Dはすでに所有権を喪失していると反論する。また、BはDに損害を与えるという不当な動機に基づき契約を締結しており、背信的悪意者と評価できる
↓そうだとして、
背信的悪意者からの転得者は177条の第三者として保護されるかどうかは相対的に判断される
↓
Cは契約締結に当たり、AD間の売買契約の存在やAの無資力を知っていたが、BにDを害する意図があることは知らなかった。そのため、Cは悪意者であるとしても、信義則に反するような事情はない
↓以上より、
Cは背信的悪意者ではなく、177条の第三者に該当する。
↓よって、
請求1は認められない
・詐害行為取消権(424Ⅰ)
:債務者が債権者を害するためにした行為の取消しを裁判所に求めることができる債権者の権利
↓
取消訴訟の被告は受益者または転得者であり、債務者は被告適格を有しない
↓(被告が受益者の場合の要件)
①被保全債権が存在していたこと
②被保全債権の発生原因が詐害行為前に生じたものであること
③債権者にとって自己の債権を保全する必要があること(債務者の無資力)
④債務者が財産権を目的とする行為をしたこと
⑤その行為が債権者を害するものであること(詐害行為)
⑥その行為が債権者を害することを債務者が知っていたこと(債務者の詐害意思)
↓(被告が転得者(受益者から転得した者)の場合の要件)
①-⑥は受益者と同じ
⑦受益者が悪意であること
⑧転得者がその転得の当時、債務者がした行為が債権者を害する事実を知っていたこと(424の5①)
・請求2について
DはCに対し、詐害行為取消権を行使し、Aへの所有権移転登記手続を請求している
↓(詐害行為取消権の要件)
詐害行為取消権は責任財産の保全を目的とした制度であるため、被保全債権は金銭債権である必要がある
↓しかし、
①特定物債権である履行請求権も履行不能などに至れば填補賠償請求の金銭債権となり、被保全債権は存在するといえる
↓また、
②AD間の売買契約は詐害行為前の契約であり、③Aは十分な資力を有しておらず、④⑤⑥Aは債権者を害することを知りながら時価4000万円相当の甲土地を2000万円でBに売却しており廉価売却による財産減少行為であり、⑦Bもそれを知りながらCへ売却しており、⑧Cもそのことを把握していた。
↓以上より、
Dの詐害行為取消権は認められる
↓よって、
請求2は認められる
〔設問2〕Fはその所有する乙建物をGに賃貸する契約をGとの間で締結しGに引き渡した。そして、FはHから1000万円を弁済期を2年後とする約定で借り受け、その借入金債務(債務α)を担保する目的で乙建物をHに譲渡する契約をHとの間で締結した(契約⑦)。また、Fは借入金債務の弁済期が経過するまで乙建物の使用収益をする旨が合意された。その契約に基づき、Hへの乙建物の所有権移転登記がされた。Gはその後もFに対して賃料を支払っていたが、所有権移転登記されていることを知り、賃料を支払わなくなった。Fは債務αの弁済をしないまま、債務αの弁済期経過前に発生した賃料と弁済期経過後に発生した賃料の支払いをGに請求した(請求3)。
主張(ア)G:乙建物がHに譲渡されたので、Fに対して賃料を支払う必要はない、主張(イ)F:Hへの所有権移転登記がされているが、これは契約⑦に基づくものであって、賃貸人の地位が直ちにHに移転する効果を生ずべき譲渡があったわけではない、主張(ウ)F:仮にそのような譲渡があったとしても債務αの弁済期が経過するまでFが乙建物の使用収益をする旨の合意があるから賃貸人の地位は自分に留保されている、という各主張の根拠を説明した上で、Fの反論の当否を検討し、債務αの期限に留意して、請求3が認められるか論じなさい
・賃貸借契約(601)
:当事者の一方が相手方に対し、ある物の使用収益をさせることを約束し、相手方がこれに賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約束することによって成立(諾成、双務、有償契約)
↓
・賃貸人の義務
1)賃借物を使用収益させる義務
2)修繕義務(606Ⅰ)
3)賃借人の法益に対する保護義務
・賃借人の義務
1)賃料支払義務(601、614)
2)用法遵守義務(616、594)
3)賃借物保管義務(400、615、606Ⅱ)
4)賃貸人の法益に対する保護義務
・不動産所有権の譲渡と賃貸人の地位の移転
↓
不動産賃借人が当該不動産の譲受人に賃貸借を対抗することができるときは当該不動産の賃貸人たる地位はその譲受人に移転する(605の2Ⅰ)
↓(対抗要件)
・不動産賃貸借の登記(605)
・借地権者が登記されている建物の所有(借地借家法10)
・建物の引渡しを受け、その物権を取得(借地借家法31)
・譲渡担保
:AがBに融資するにあたり、Bが所有する機械甲の所有権を受けるというような担保形態。Bが借入金債務を弁済したならば甲の所有権はBに復帰するが、弁済がされない場合は私的実行を経て、甲の所有権はAに確定的に帰属する
↓
・私的実行
:裁判所の競売手続を介さない担保実行
↓(対抗要件)
・不動産譲渡担保:登記
・動産譲渡担保:引渡しまたは動産譲渡登記
・債権譲渡担保:確定日付のある証書による通知もしくは承諾または債権譲渡登記
・譲渡担保の法的性質
1)所有権的構成
:設定契約時に所有権が完全に譲渡担保権者に移転
2)担保権的構成
:設定契約時には所有権は移転せず、私的実行によってはじめて譲渡担保権者に移転
3)設定者留保権
:譲渡担保設定契約時に目的物の所有権は設定者から譲渡担保権者に移転するものの、この所有権移転は譲渡担保権者の有する被担保債権を担保するためにされたものであるから譲渡担保権者のもとでの所有権は担保的な制約を受けている
→設定者のもとになんらかの物権的地位が留保されている
→譲渡担保権者に目的物の所有権が確定的に帰属するためには譲渡担保権の実行としての私的実行がされなければならない
・主張(ア)について
FからHに乙建物が譲渡された結果(605の2Ⅰ)、賃貸人の地位はHに移転しており、Gは既に賃貸人たる地位を失っており、賃料支払請求ができないと主張
・主張(イ)について
乙建物はあくまで債務αの担保目的でHに譲渡したのであり、このような譲渡担保は605条の2第1項にいう「譲渡」に該当しないと主張
・主張(ウ)について
譲渡担保設定により賃貸人の地位がHに移転するとしても、不動産譲渡人・譲受人間の賃貸人の地位を譲渡人に留保する合意(留保合意)と、不動産を譲受人が譲渡人に賃貸人に賃貸する合意(譲渡当事者間の賃貸合意)があれば、賃貸人の地位をFに留保することができる(605の2Ⅱ)
・請求3について
譲渡担保設定によって担保権者にいわば慣習上の物権である設定者留保権が差し引かれた所有権が移転する。あくまで担保目的ではあるものの、法形式としては所有権が移転することを考えると、605条の2第1項の「譲渡」による賃貸人の移転が生じることは否定できない。担保としての実質だけを根拠に賃貸人の移転を否定するならば、賃貸人の地位の帰属が曖昧になり、賃貸人の地位を賃借人に対抗するために登記を要した規定(605の2Ⅲ)の意義すら没却しかねない。
↓しかし、
譲渡担保設定により設定者Fに認められる利用権は物的な設定者留保権である。そうすると、賃借権よりも強い利用権原がFに認められる以上、厳密に賃貸合意ではないことだけを理由に605条の2第2項の適用を否定すべきではない。そして、譲渡担保権者Hに使用収益権はなく、設定者Fも利用権原に基づき賃貸人の地位を主張する以上、譲渡担保設定契約の合理的解釈により賃貸人の留保合意を認めることができる。
↓そして、
譲渡担保も担保の一つである以上、実行による清算というプロセスの省略は認められない。譲渡担保権の実行を完了し、設定者の使用収益を終了させるには、弁済期後に、第三者に処分するか(処分清算)、清算金を適正に評価してそれを設定者に提供するか(帰属清算)、いずれかの方法を採る必要がある。本問において、弁済期経過後、Hはそのいずれの手続も実行していない。そうすると、手続が完了するまでFは賃料を収受することができる。
↓以上より、
請求3は認められる
〔設問3〕Kは丙不動産を所有し、Kには子Lがいたが、かわいがっていた姪Mに丙不動産を与える旨の贈与契約を書面で締結した。その後、KとMの関係は悪化し、Kは丙不動産をN県に遺贈する旨の自筆証書遺言を作成し、LとN県に通知した。K死亡後、MはLに対し、贈与契約に基づき丙不動産のMへの所有権移転登記手続を求めた(請求4)。これに対し、Lは「贈与契約はその後にKの遺贈する旨の遺言により撤回されたはずである。」と主張した。
その主張の根拠を説明の上、Mからの反論を踏まえ、請求4が認められるか。
・死因贈与(554)
:贈与者の死亡によって効力が発生する贈与
↓
・書面により契約した場合は解除できない(550)
・遺贈(964)
:被相続人が遺言によって他人に自己の財産を与える処分行為
・相続(882)
:被相続人の死亡により開始
・相続人
:被相続人の相続財産を包括承継することのできる一般的資格を持つ人
↓
・第一順位の相続人:子(887Ⅰ)
・第二順位の相続人:直系卑属(889Ⅰ①)
・第三順位の相続人:兄弟姉妹(889Ⅰ②)
・相続の効力(896)
:相続により、被相続人のもとで形成されてきた財産関係が一体として相続人によって承継される。ただし、被相続人の一身に専属したものは相続の対象ではない
・遺言の撤回(1022)
:遺言は表意者の最終意思に対して法秩序が効力を与えようとしたものであるから、その裏返しとして、遺言者の生存中には、遺言により行われた意思表示を撤回するのは自由である
・撤回擬制
:以下の場合、遺言は撤回されたものとみなされる
1)前後の遺言が内容的に抵触する場合(1023Ⅰ)
2)遺言の内容とその後の生前処分とが抵触する場合(1023Ⅱ)
3)遺言者が故意に遺言書または遺贈目的物を破棄した場合(1024)
・Mは請求4をもってKM間の死因贈与の履行を求め、Lに所有権移転登記請求権を行使している。LはKの唯一の子であり、Kの権利義務を包括承継している。また、死因贈与は書面によるため、解除はできない。これに対し、Lは死因贈与は自筆証書遺言をもって撤回されたと反論している(1022、1023Ⅰ)。
↓確かに、
死因贈与は契約であり、単独行為たる遺贈とは異なる。しかし、死後の財産処分という点において、遺贈と類似するため、死因贈与についても贈与者の最終意思の尊重が妥当する。したがって、死因贈与にも1022条、1023条が準用される(554)。
↓以上より、
請求4は認められない
参考文献
:民法〔第3版〕・潮見佳男(有斐閣)
民法判例百選Ⅰ〔第8版〕、民法判例百選Ⅱ〔第8版〕、民法判例百選Ⅲ〔第2版〕(有斐閣)
司法試験の問題と解説2022・法学セミナー編集部(日本評論社)