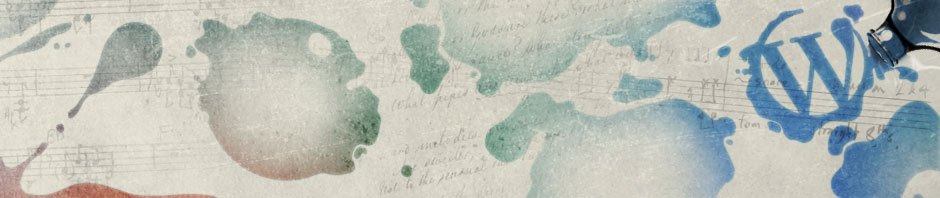〔設問1〕(1)ア 請求1、AのCに対する土地所有権に基づく物権的返還請求
・物権的返還請求権
:物権を有する者に帰属すべき物を第三者が占有しているときに物権を根拠として、その第三者に対し、その物の占有の回復(物の引渡し)を求めることができる権利
・契約①:他人物賃貸借(559(561により債権的に有効))
・賃貸借(601)
:当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによってその効力を生ずる。
・賃貸人の義務
1.賃借物を使用収益させる義務(601)
2.修繕義務(606)
3.賃借人の法益に対する保護義務
・賃借人の義務
1.賃料支払義務(601、614)
2.用法順守義務(616、594Ⅱ)
3.賃借物保管義務(400、615)
4.賃貸人の法益に対する保護義務
・相続の一般的効力(896)
「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない。」
・無権代理
:代理行為をした者がその法律行為について代理権を有していないか、または代理権を有しているが、授権された範囲を越えて代理行為をした場合。
↓効果
代理権を欠いた代理行為は本人に帰属効果しない。本人が追認すれば効果帰属する。(113)
・無権代理人が死亡して本人が相続した場合
:相続人である本人が「本人としての地位」に基づいて被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても信義則に反するものではない。(本人の無権代理人相続 最判S37.4.20 Ⅰ-35)
〔設問1〕(1)イ 請求1、CのBに対する損害賠償請求権を被担保債権とする土地の留置権の主張
・留置権(295)
「他人の物の占有者はその物に関して生じた債権を有するときはその債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでない。」
債権の弁済を心理的に強制することができる権利。
・留置権の成立要件
1.留置権者が「他人の物」を占有していること。
2.留置権者が物に関して生じた債権(被担保債権(ex.費用償還請求権、損害賠償請求権等) を有すること。-被担保債権と物との牽連性
3.留置権者の被担保債権が履行期にあること。
・留置権者の成立阻却事由
1.占有が不法行為によって始まった場合(295Ⅱ)
2.占有開始後の権限喪失
〔設問1〕(2)ア 請求2、DのAに対する賃料一部返還請求
・賃借物の一部が使用収益できなくなった場合にそれが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は使用収益できない部分の割合に応じて減額される。(611Ⅰ)
賃料の支払時期は特約等がない場合は後払い(614)
↓(原則)
そのため、前払いの賃料の一部減額はできない。
↓(修正)
しかし、611条1項の趣旨に照らせば類推適用により、賃借人が使用収益できなかった期間、部分に相当する賃料は減額され、既払いの賃料の返還請求ができる。
〔設問1〕(2)イ 請求3、DのAに対する修繕費用の償還請求
・原則:賃貸人に修繕義務(606Ⅰ)、賃借人に通知義務(615)
↓
賃借人が修繕(607の2)
①賃借人から賃貸人に通知、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
②急迫の事情があるとき
↓急迫な事情はなく、DからAに対して通知していないため、問題となる。
607条の2の趣旨
:賃貸人が自ら修繕する機会を確保することにより、賃借人による過剰な必要費償還請求を制限することにある。
↓よって
Dの必要費償還請求(608)を認めつつも適正額を超えてしまった部分についてはDの通知義務(615)違反を原因とした債務不履行に基づく損害賠償請求との相殺。
↓以上より
DからAに対して、修繕費用の一部が償還請求として認められる。
〔設問2〕IのFに対する物権的返還請求
・錯誤
:表意者の認識しないところで表意者の主観と現実との間に食い違いがある場合
「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」にのみ、表意者はその意思表示を取り消すことができる。(95Ⅰ)
・表示行為の錯誤(95Ⅰ①)
:意思表示に対応する意思を欠く錯誤
・行為基礎事情の錯誤(95Ⅰ②)
:表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
↑
「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」(95Ⅱ)
(例外)
・表意者に重大な過失があるときは表意者は錯誤を理由として、意思表示を取り消すことができない。(95Ⅲ)
(例外の例外)※以下の場合、取り消すことができる。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(95Ⅲ①)
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(95Ⅲ②)
・錯誤による意思表示の取消しはこれをもって善意無過失の第三者(取消し前)に対抗することができない。(95Ⅳ)
・第三者
:錯誤に基づく契約当事者以外の者で錯誤に基づいて作出された法律関係につき、錯誤取消し前に新たに独立した法律上の利害関係を持つに至った者。
参考文献
:民法〔第3版〕・潮見佳男(有斐閣)
民法判例百選Ⅰ〔第8版〕、民法判例百選Ⅱ〔第8版〕、民法判例百選Ⅲ〔第2版〕(有斐閣)
司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)