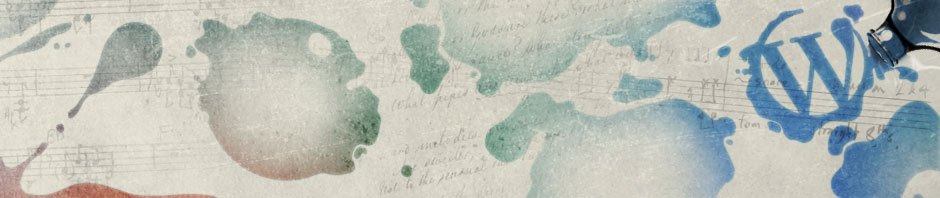工事中の現場監督から連絡があった。「シャッターボックスが壁に当たってきます。どうしましょうか。」
どういうこと?最初、何を言っているか分からなかった。

この建物は準耐火建築物のため、隣地境界線から5mの範囲内の2階以上の開口部は防火設備にする必要がある。ちなみに、「防火設備」とは、建築基準法に規定されている火災発生時に火の延焼を防ぐための設備で、窓ならガラスに金属網が入っているものである。ただ、この開口部は周囲を壁や格子で囲まれており、加えて隣地側は通路となっているので、実際に近隣で火災が起きても延焼する可能性はかなり低い。だが、そんな実際の状況は関係なしで杓子定規に法律を当てはめると防火設備にする必要があるため、仕方なく防火設備にせざるを得ないという開口部である。
また、住宅用サッシにも防火設備の設定はあるが、どのメーカーも最大でも幅1.6m高さ2.2m前後の大きさで選択肢がとても少ない。そのため、計画では幅や高さともに住宅用の防火設備では大きさが不十分なため、防火設備ではない一般サッシを設置して外部に防火シャッターを付けることになった。
だが、敷地は街中で準防火地域にあり、かつ、混構造の3階建てのため、高さ方向の制約がある。そして、その制約に逆行する建築主要望として天井高を高くとりたいという要望があった。可能な限り、天井高は高くとり、かつ、開口部もその天井高にできる限り合わせるように計画したが、シャッターボックスは窓のさらに上に設置する必要があり、一部、壁とシャッターボックスが干渉してしまった。
RevitやTwinmotionで実物に近い状態で検討を重ねて、計画内容を把握していたにも関わらず、シャッターボックスが壁と干渉するという初歩的な問題で急遽対策を検討する必要が出てきた。だが、ピンチはチャンスではないが、だからこそ元の計画よりもより良い案がないかと調べたり、現場監督の意見を聞きながら、防火設備の木製サッシや折れ戸の商品を見つけ出し、代替案を4案考え、それを建築主に提示した。それぞれの案のメリットデメリットを建築主に説明し、建築主の意向も踏まえながら、結局、元の計画である、一般サッシ+防火シャッターの仕様で壁に当たらない程度に狭めるという結論に至った。
設計という仕事はデザインや利便性の検討も重要だが、「確認」することが最も重要だと思う。法的制限、建築主との打合せ内容、建材の仕様・寸法・性能、等。確認作業は手間もかかるし、それを行ったからと言って建物の仕上がりが格段に良くなる訳ではない。だが、手戻りを防いだり、無駄なコストの発生を抑制したり、いろいろとメリットも大きい。その確認作業のために設計図面を丸一日、見返すこともあるし、CAD以外のソフトで多角的にその作業を行ったりすることもあるが、設計業務を20年もやっていれば大きな抜けはないものの、小さな抜けはどんなに確認を繰り返してもゼロにはならない。だが、ゼロにする努力はすべきであるし、ゼロにならなくてもその姿勢はきっと建物の完成に反映されているはずだと信じている。